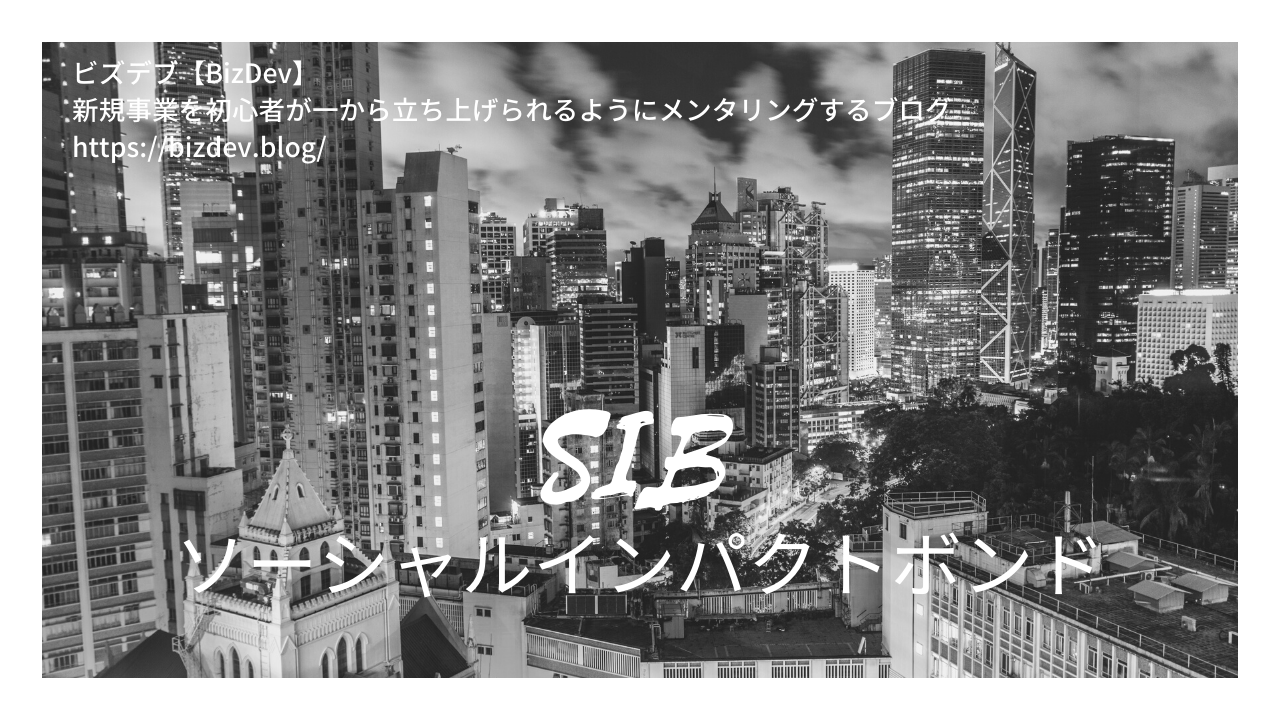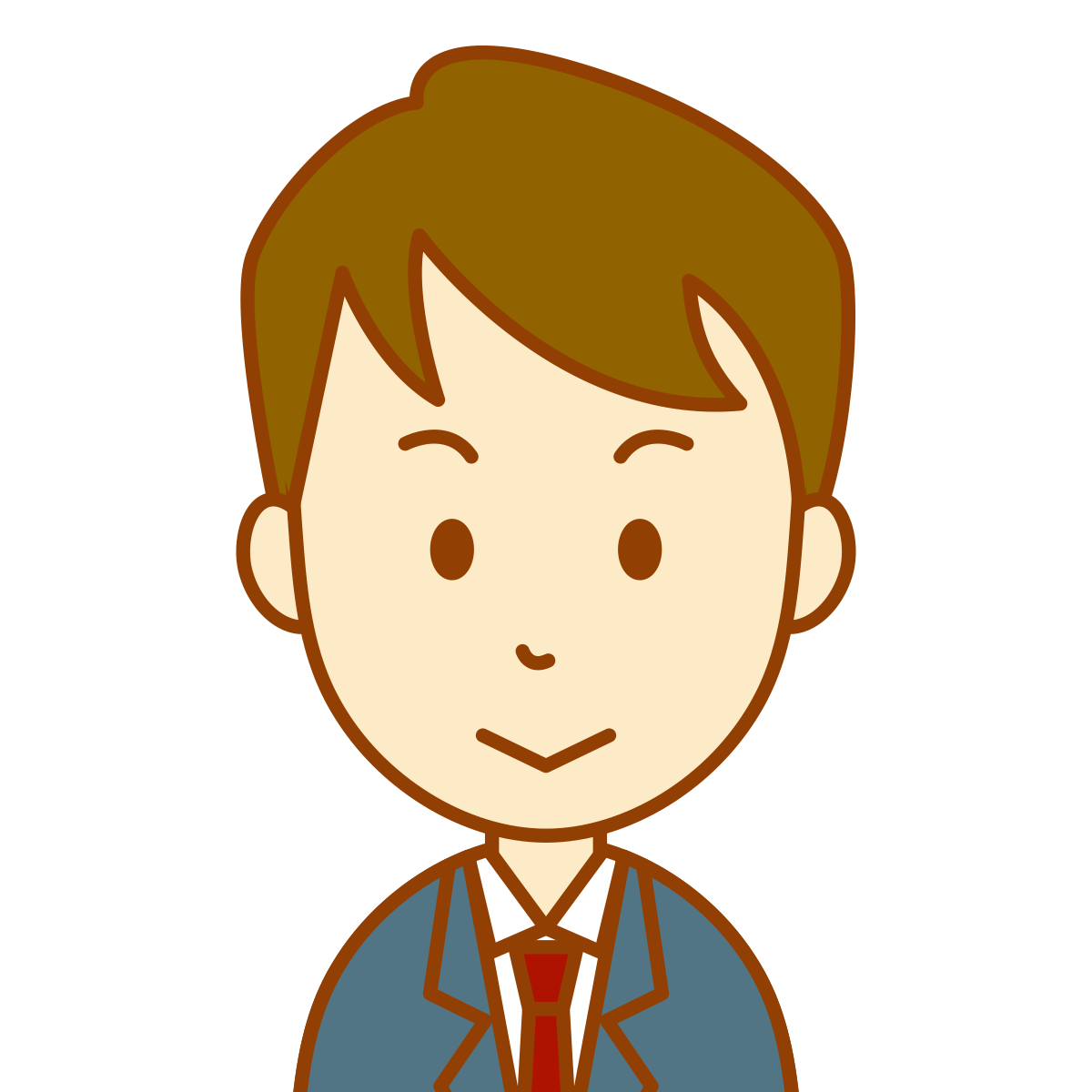
ソーシャルインパクトボンドという行政と民間事業者間の取り組みが進んでいると聞いた事があるのですが、どのような仕組みなのですか?
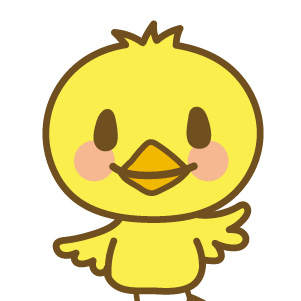
社会課題の解決を目指す成果志向型の取り組みとして期待されている仕組みです。本格的な導入はまだまだこれからというところですが、ヘルスケアにおいては糖尿病の重症化予防などで先行事例が出てきていたり、今後は一気に普及する可能性もありますので、概要などを押さえておきましょう。
ソーシャルインパクトボンド(SIB)とは
ソーシャルインパクトボンドとは、民間資金を活用して革新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成果(社会コストの効率化部分=アウトカム)を支払の原資とする仕組みを指します。
海外では既に、民間事業者が活動した成果(行政コストの削減など)を数値化し、自治体等がその成果報酬を支払うビジネスモデルが存在し、民間資金の活用が進んでいます。
つまりは、これまでは100%行政が負担していたコストの一部を先行投資として投資家やサービス提供者が負担し、アウトカムに応じて成果報酬を支払う事で、行政の負担コスト全体を抑制するという事をねらった仕組みです。
ソーシャルインパクトボンド(SIB)の推進体制
ソーシャルインパクトボンドを実施する際には、中立的に事業成果を評価する第三者評価機関や、行政・資金提供者・サービス提供者などでビジネススキームを構築する必要があります。
| プレイヤー | 想定組織 |
|---|---|
| 行政 | 中央政府、都道府県、基礎自治体 |
| 中間支援組織 | 財団など、非営利組織(NPO)、シンクタンク、コンサル会社 |
| サービス提供者 | 非営利組織(NPO)、民間事業者 |
| 資金提供者 | 投資家、財団 |
| 評価アドバイザー | シンクタンク、コンサル会社 |
| 第三者評価機関 | 大学、監査法人など |
行政については「行政負担の削減」、サービス提供者は「革新的なサービスの社会実装」など、それぞれのプレイヤーがお互いにメリットを享受し合える関係性の構築が必須となります。
ソーシャルインパクトボンド(SIB)のテーマ例と事例
自治体の歳出決算額に占める固定経費の割合は非常に大きいですが、ソーシャルインパクトボンドによって固定経費の効率化が可能になります。
初期投資を民間の指揮で賄う事で、自治体としては持続可能な事業を展開する事が可能になります。
ソーシャルインパクトボンドが検討・実施されている対象テーマの例は以下の通りです。
- 認知症予防
- 糖尿病重症化予防
- がん検診受診率向上
- 介護予防
- 健康づくり
- 児童養護(特別養子縁)
- 若者就労支援(アウトリーチ)
- 起業支援
- 移住促進
- こどもの貧困
日本においては以下の事例が有名です。
| 自治体 | 取り組み内容 |
|---|---|
| 東京都八王子市 | 大腸がん検診受診勧奨 |
| 兵庫県神戸市 | 糖尿病性腎症重症化予防 |
| 広島県 | 大腸がん検診受診勧奨 |